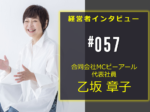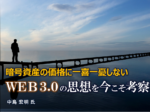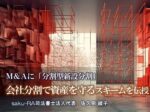オーバーツーリズムの原因は何か? 外国人観光客問題とは
- 2025/8/27

日本の人気観光地を訪れた際に目にする光景は、過去とは大きく様変わりしています。
狭い路地が外国人観光客であふれかえり、地元住民が日常的に使う生活道路が常時混雑し、歩行すら困難な状況が生まれています。目につくゴミのポイ捨て、公共交通機関の慢性的な満員状態、住宅街にまで響き渡る大きな話し声。
これらはオーバーツーリズムと呼ばれる現代の観光が抱える深刻な病巣の表れです。
訪日外国人観光客、いわゆるインバウンドの急速な増加は、確かに地域経済に大きな恩恵をもたらしました。ホテルや土産物店、飲食店など、観光関連産業にとっては大きな追い風となったことは間違いありません。しかし、一方で、観光地が本来持つ受け入れキャパシティをはるかに超える過剰な観光客の流入が、地域住民の日常生活、地域の環境、そして貴重な文化遺産に深刻かつ時に不可逆的な悪影響を及ぼす問題を引き起こしています。
京都の古い町並み、鎌倉の由比ガ浜通り、浅草の仲見世通り、あるいは地方の秘湯として知られた温泉地など、外国人問題は多岐にわたり、かつ深刻化しています。オーバーツーリズムは単なる外国人による混雑という表面的な問題ではなく、地域社会の持続可能性そのものを脅かす根深い社会課題です。
なぜオーバーツーリズムが発生するのか、その複雑で多層的な根本原因を外国人観光客問題というレンズを通じて徹底的に掘り下げてみたいと思います。同時に、観光業の現場で苦闘する中小企業経営者の方々が直面する現実的な課題、そして日々の生活の中で増え続ける外国人観光客に辟易とし、ときに疎外感さえ覚える地域住民の方々に向けた具体的なヒントを模索してみましょう。
オーバーツーリズムが起きる背景
観光立国政策とインバウンドの爆発的増加
オーバーツーリズム現象を理解する上で、土台となったのは、国を挙げて推進されてきた観光立国政策です。2000年代に入り、日本政府は人口減少や地方衰退、経済活性化の切り札として観光産業、特にインバウンド(訪日外国人旅行者)の拡大に本腰を入れ始めました。数値目標を次々と掲げ、それを達成するための様々な施策が矢継ぎ早に打ち出されました。
代表的なものには、アジア諸国を中心としたビザ要件の大幅な緩和や免除、大型クルーズ船の受け入れ拠点整備と受け入れ拡大、消費税免税制度の拡充と手続きの簡素化、空港や主要駅での多言語対応の強化、そして海外での大規模な観光プロモーションキャンペーンなどがあります。この一連の政策は大きな成果を上げ、訪日外国人旅行者数は着実に、そして驚異的なスピードで増加の一途をたどりました。この急激な増加は、特に京都や浅草などの世界的に著名な観光地に、前例のない数の観光客が集中する素地を作り出しました。観光客の増加は地域経済にとって確かに追い風ではありましたが、そのスピードと規模があまりにも急激であったため、多くの受け入れ側の地域社会やインフラが対応しきれない状況を生み出し、オーバーツーリズムという歪みを顕在化させる結果となってしまったのです。
爆買いから体験消費へのシフト、人気観光地への集中化
訪日外国人観光客の数が膨れ上がると同時に、その旅行スタイルも劇的に変化してきました。かつては中国人観光客を中心とした高級家電製品やブランド品、化粧品などのモノを大量に購入する爆買いが主流でしたが、近年は日本のコト、つまり固有の文化や伝統的な生活様式、食文化、自然景観などを深く体験し、その価値を味わうことに重きを置く体験型消費へと重心が大きく移行しています。古都の寺院や神社での参拝体験や庭園鑑賞、温泉地での湯治文化の体感、茶道や華道、書道といった伝統文化のワークショップ、着物や浴衣のレンタルと街歩き、地元の市場で旬の食材を探す、農家民宿での農業体験、あるいはアニメやドラマのロケ地を巡る聖地巡礼など、多様で個性的な体験を求めて日本を訪れる外国人観光客が増えています。この変化自体は、日本の魅力の多様性と深みが国際的に認められた証左であり、本来は大いに喜ばしい傾向です。
しかし、この体験型消費には、特定の象徴的な人気スポットや、SNSで話題のインスタ映えする場所に観光客が集中しやすいという側面が強くあります。多くの観光客が「本物の京都を感じたい」「代表的な日本の風景を写真に収めたい」と願い、情報で共有された限られた場所、いわゆる定番スポットに殺到する傾向が加速しているのです。結果として、これらの有名観光地は常に過剰な人で溢れかえり、本来の魅力である静けさや情緒が失われてしまう皮肉な状況が生まれています。
SNSの爆発的普及が生むバズりの功罪
オーバーツーリズムを加速度的に悪化させる最大の要因の一つが、SNSの爆発的な普及とその圧倒的な影響力です。InstagramやTikTok、YouTube、Twitterなどのプラットフォームは、美しい写真、感動的な動画、旅行体験談を瞬時に世界中の何百万人、時には何千万人ものユーザーに拡散する力を有しています。これにより、特定の場所や瞬間(例えば、ある神社のひときわ美しい鳥居を背景にした写真、ある寺院の苔むした神秘的な庭園の一景、ある路地からの絶景夕日、特定のレストランの見た目も鮮やかな一品、あるいは一匹の猫が佇む町角など)が「絶対に行くべきスポット」「隠れた名所」「一生に一度の体験」として世界的な注目を集め、一気にバズる現象が日常茶飯事になっています。SNSは、観光地の隠れた魅力を広め、未知の場所を旅行者に発見してもらう強力なツールである反面、観光客の流れを特定の場所に極端に偏らせ、その場所のキャパシティを瞬時に超え、圧迫をかけてしまうリスクをはらんでいます。一度バズった場所は、その人気が自然に収束するまで、長期間にわたって地域住民の生活空間や地元の環境、そして近隣の店舗の営業などを圧迫し続けることになります。さらに、SNSのアルゴリズムが類似コンテンツをユーザーに繰り返し提示し続けることで、特定スポットへの集中現象が長期化する傾向も見逃せません。このデジタル時代の観光誘導が、日本におけるオーバーツーリズムを引き起こしていると言えます。
LCCとビザ緩和による旅行の大衆化
オーバーツーリズムを支える構造的な背景として、海外旅行そのものがかつてないほど気軽に安くなったことも挙げられます。この変化を牽引したのは、LCC(格安航空会社)の国際線への本格参入と航空運賃の大幅な低下です。特に地理的に近いアジア諸国(韓国、台湾、中国、香港、マカオ、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピンなど)からのアクセスが飛躍的に容易になり、旅行期間も週末を利用した2泊3日や3泊4日といった短期間の気軽な旅行が主流になりつつあります。さらに、政府の観光立国政策の一環として、多くの国に対するビザ要件の緩和や免除が着実に進み、海外旅行の手続き上のハードルは大きく下がりました。パスポートさえあれば気軽に日本を訪れられる環境が整備されたのです。さらに、国内での移動を支える新幹線や高速バスのネットワーク拡充、レンタカー会社の多言語対応、そして都市部での地下鉄やバスの路線図・アナウンスの多言語化など、国内交通網のインバウンド対応も急速に進み、観光客が日本国内を自由に、ストレスなく移動しやすくなっています。
旅行の大衆化は、より多くの人々に海外旅行の機会を提供したという点で大きな意義があります。しかし、結果として、ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始、あるいは桜や紅葉の見頃シーズン、特定の週末や大型イベント開催時期などに、短期間で大量の観光客が特定の観光地に集中して流入する原因を作り出しています。特に、大型連休や絶好の行楽シーズンには、その集中度はものすごく、地域の日常的な生活を完全に麻痺させてしまうことも珍しくなくなりました。
オーバーツーリズムの根深い原因
観光地の受け入れキャパシティの厳しい現実
オーバーツーリズムの本質は、端的に言えば「観光客の需要が、観光地の供給能力(キャパシティ)を持続的に大幅に超過している」状態です。このキャパシティ超過は、多くの日本の人気観光地が抱える根本的な制約によるものと言えます。
京都や奈良のような歴史の町並みが色濃く残る古都、鎌倉のような三方を山に囲まれ海に面した独特の地形を持つ街、あるいは沖縄の離島や北海道・東北の山間部に点在する温泉地などは、そもそも地理的・歴史的な理由から都市的な発展に強い制約があり、受け入れ能力にそもそもの限界があります。具体的には、自動車一台がやっと通れるような狭い生活道路(場合によっては車両通行不可)、極めて限られた駐車場スペース、小規模な駅舎やバスターミナル、対応可能な路線バスやタクシーの台数不足、そして何よりも地元住民の生活が前提となっている小規模な生活インフラなど、地域のインフラは地元住民の日常的な生活規模と、過去の穏やかな観光客数を前提に設計・整備されているのが実情です。これらのインフラは、急激で大規模な観光客の流入という想定外の負荷に耐えられるようには作られていません。その結果、慢性的な交通渋滞やバスの大幅な遅延、歩行者専用道路での身動きが取れないほどの混雑、ゴミ処理能力の超過による路上への散乱ゴミの増加、公衆トイレの不足や劣悪な衛生状態の常態化、住宅街において大騒ぎする外国人観光客の存在など、様々な形で問題が噴出します。観光地の魅力の根幹である静けさ、落ち着いた雰囲気、歴史的情緒などは、こうした混雑と喧噪の中で急速に失われ、外国人観光客自身の体験の質も大きく低下してしまいます。さらに深刻なのは、住民にとっては、救急車や消防車といった緊急車両の走行さえ困難になるなど、生命・財産の安全に関わる重大な問題に発展するケースが現実に懸念されている点です。このキャパシティの限界は、オーバーツーリズム問題の根源的な原因の一つなのです。
マスツーリズム中心の観光政策
国レベルでの観光政策、特にインバウンド政策は、長らく「数を増やす」こと、つまり観光客数の最大化と消費額の拡大に主眼が置かれてきました。具体的な数値目標(例えば、「2020年までに年間訪日外国人旅行者数4,000万人」といった目標)の達成自体が政策の成功指標とされ、その数値を達成するための手段(ビザ緩和、免税拡大、プロモーション予算の重点投入など)が優先されてきた感は否めません。しかし、この数の拡大路線は、その受け皿となるべき地方自治体や個々の観光地のキャパシティ、そして何よりもそこで生活を営む地域住民の日常生活への影響についての十分な対策を講じることにまで、十分に考えられてこなかったのが現実です。国と地方の間で、観光政策の目標や優先順位に大きなズレが生じていたとも言えます。自治体レベルでも、この急激な変化の波に十分に対応しきれず、苦慮しているケースが少なくありません。効果的な観光客の分散策(時間帯による分散、周辺エリアへの分散、新たな観光ルートやコンテンツの開発)の立案・実行には、予算や観光専門人材が不足しています。観光客向けの明確で実効性のあるルール・マナーの啓発も、多言語対応や発信方法の課題があり、不十分です。そして何よりも、地域住民の声をしっかりと汲み取り、生活環境の保全と観光のバランスを取るための観光計画や条例の策定が、観光客の増加に追いついていないのが現状です。観光収入の増加が地域の観光事業者にとって重要であることは間違いありませんが、その持続可能性を維持するためには、外国人観光客の質や適正量をコントロールする視点が必要でしょう。観光地としての魅力そのものが、増えすぎた観光客によって損なわれ、住民の生活が破壊されてしまっては、経済効果も長続きせず、元も子もありません。
文化・習慣・言葉の壁が生む摩擦とマナー問題
外国人観光客の急増は、文化や習慣、行動様式の違いに起因するトラブルを増やし、地域住民のストレスを高める大きな要因となっています。代表的な問題としては、路上や公園でのゴミのポイ捨てや、複雑な分別ルールの無視(特にコンビニ周辺や観光バスの停車場、住宅街の隅)、早朝や深夜の住宅街における大きな声での会話や騒音問題、私有地や住民の生活空間(ときには家の玄関先や庭先、ときには民家の窓を覗き込むような)への無断立ち入りや無断写真撮影、神社仏閣などの宗教施設や歴史的建造物における不適切な行動(柵の内側への立ち入り、飲食や喫煙、服装のルール無視、静粛を守らないなど)などが頻発しています。これらは、必ずしも観光客に悪意があるわけではなく、自国での常識や行動様式の違い、訪れた観光地で具体的にどのように振る舞うべきか(あるいは厳しく禁止されているのか)に関する情報の不足、単なる無理解や言語によるコミュニケーションの難しさから生じることが非常に多いと思われます。しかし、こうした行動が日常的に、しかも大勢の観光客によって繰り返されることで、住民のストレス、ときにはプライバシー侵害への不安感は増加し、次第に外国人観光客そのものへの嫌悪感や排他的な感情(最近では日本人ファーストといった主張としてあらわれることもあります)を生み出す温床となってしまいます。
言語の壁は非常に大きいので、住民側がそれぞれの外国人観光客に注意を促したり、ルールを丁寧に説明して理解してもらったりすることは、現実的に非常に大変です。また、外国人観光客側も、日本の地域のルールやマナーを知る適切で分かりやすい情報源(目立つ場所にある多言語サイン、多言語パンフレット、宿泊施設でのチェックイン時の丁寧な説明など)が不足している場合、知らず知らずのうちに地域の迷惑となる行動を取ってしまっているのかもしれません。
住民感情の悪化
オーバーツーリズムは、経済的な問題も深刻に内包しています。確かに、外国人観光客の増加は、地域全体としての経済効果(雇用創出など)をもたらします。しかし、その恩恵がその地域全体に、そして特に日常生活の不便を強いられ、迷惑を受けている住民に、十分に還元されないケースが多くあるのです。これが住民の不満を生む原因となっていると考えられます。
大型ホテルチェーンや大規模商業施設、大手旅行会社、クルーズ船会社など、資本力のある大企業には大きな利益がもたらされる一方で、地元の中小企業、例えば家族経営の小さな旅館や民宿、個人商店、町のレストランやカフェ、小規模な土産物店などは、人手不足や人件費高騰、賃料の上昇、物価の高騰といった経営課題に直面しつつも、必ずしも外国人観光収入増の恩恵を十分に享受できていないとも言えます。例えば、団体観光客は事前にパッケージ化された行程に沿って行動し、あらかじめ決められた大型レストランなどで消費することが多く、地元の中小零細事業者にはお金が落ちにくい構造になっている場合が多いでしょう。さらに、観光バスによる排気ガスや騒音、混雑に日常的に悩まされながら、自分たちの生活や事業には直接の利益やメリットが見えにくい住民にとっては、外国人観光客の増加は迷惑でしかないと思ってしまうでしょう。地価や物価が外国人観光客向けに吊り上がり、地元住民の生活コストが上昇する逆効果も生まれています。「観光で潤っているのは一部の業者だけ」という不満は、観光そのものへの反発感情を生み出すかもしれません。
観光公害としての環境負荷の増大
物理的な混雑やマナー問題だけでなく、環境への過大な負荷も、オーバーツーリズムが引き起こす深刻な結果です。
膨大な数の観光客が排出する大量のゴミ(ペットボトル、弁当の容器、お土産の包装、タバコの吸い殻など)が、路上や河川敷に散乱したり、景観を著しく損ねたり、河川や海を汚染する原因にもなります。自然豊かな国立公園や山岳地帯、美しい海岸線を持つ離島などの観光地では、登山道の荒廃や植生の破壊、野生動物の生息域への無断侵入やストレス、踏み荒らしによる貴重な植物の減少、海洋プラスチック問題の悪化など、生態系への深刻な影響が心配されています。さらに、歴史的建造物や貴重な文化財、伝統的な町並みなどは、そもそも多数の人が一度に押し寄せ、触れたり、踏み荒らしたりすることを想定して作られてはいません。継続的な過剰な人の往来は、建造物の劣化を早めますし、その修復には多くの費用が必要になります。また、そうした場所が持つ宗教的雰囲気や歴史的景観などの価値が、大勢の外国人観光客によって損なわれ、観光地が本来持つ文化的な意義が薄れてしまう恐れもあります。
世界遺産や国宝といった人類共通の貴重な文化遺産、あるいはかけがえのない自然環境を守り、次世代に確実に引き継いでいくためにも、適正な外国人観光客数の管理は、待ったなしの喫緊の課題です。オーバーツーリズムは、観光地の持続可能性を根底から揺るがす観光公害なのです。
持続可能な観光を目指すには
観光客分散戦略
オーバーツーリズムの解決策として、特定の場所・時間に集中する観光客の流れを分散させることがひとつのヒントになります。自治体や観光協会、DMO(観光地経営組織)は、メインの超有名観光スポットだけに焦点を当てたプロモーションをやめ、その周辺地域の隠れた名所や、まだ広く知られていないが魅力あふれる場所を継続的に発信していく必要があるでしょう。
例えば、京都であれば、祇園や清水寺周辺に集中する観光客を、郊外の大原や鞍馬、貴船といった自然豊かなエリア、あるいは市内でも通常の観光ルートから外れた町家が残る西陣エリア、地元の職人仕事や旬の食材に触れられる錦市場などへと誘導する、ディープ京都といった明確なコンセプトを打ち出し、魅力的な物語性を持ったコンテンツとして情報提供することが非常に有効でしょう。観光情報誌やウェブサイト、SNSだけでなく、現地の観光案内所での丁寧な説明や、宿泊施設との連携による情報提供が鍵となると言えます。
また、時間帯による分散も極めて重要です。早朝の静かな時間帯を活用した特別拝観や早朝割引サービスの提供、ライトアップや夜間特別開放を活用したナイトツアーの企画、あるいはリアルタイムの混雑予測情報を提供するスマートフォンアプリや観光案内所のデジタルサイネージなどを活用し、観光客自身が混雑を避けて行動する選択をしやすい環境を整備することも大事です。混雑状況を見える化し、代わりの時間帯や場所を教えてあげる情報提供が求められます。
さらに、テーマを変えた分散も有効です。神社仏閣巡りやインスタスポット巡りといった均一な関心だけでなく、「京野菜と食文化」「伝統工芸と職人技」「文学の舞台めぐり」「自然散策とハイキング」「現代アートと町歩き」など、多様な興味関心に応じたテーマ性のあるルートを設定し、観光客の関心を多様化させることができれば、特定スポットへの一極集中を緩和することができます。分散を促すには、魅力的な複数の観光スポットの存在と、それらへのアクセス情報(公共交通機関情報、所要時間、周辺の飲食店情報など)を分かりやすく提供することが大事です。
キャパシティ管理と予約・入場制限・課金の導入
物理的なキャパシティに明らかな限界があり、無制限な入場が環境や文化財、住民生活に悪影響を及ぼすことが明白な場所では、思い切った管理策の導入も考えるべきだと思います。世界遺産の一部区間や京都の竹林の道、自然保護区域、富士山などで、入場者数の制限や事前予約制の義務化、有料化、時間帯指定制の導入が必要でしょう。日本人観光客も外国人観光客も、一人ひとりがゆったりと鑑賞・体験できる環境を維持し、施設や自然環境、住民の生活空間を保全するための効果的な方法と言えます。これからは、混雑が深刻化する観光地において適正な観光客数を設定し、それを管理するシステムの導入が進んでいくと考えられます。
具体的な管理手法としては、事前オンライン予約の完全義務化、入場料の動的価格設定(混雑ピーク時は高く設定して需要を抑制し、閑散期や早朝・夕方は安く設定して分散を促す)、特定エリアへの入場制限や入域料の徴収、観光バスの乗り入れ台数・時間帯の規制などが考えられます。なお、これらの規制を単なる制限としてではなく、「より良い観光体験のための必要な投資」として外国人観光客にも理解してもらうための丁寧な説明が必要です。そして、スムーズな予約システムも必要です。当然ながら、地域住民の日常的な生活が損なわれないような配慮(住民パスの発行、特定時間帯の住民優先アクセス、近隣住民の無料化など)を同時に講じることも絶対条件です。住民の生活を犠牲にした観光規制になってしまうのは本末転倒と言えます。
観光マナー啓発の強化
文化や習慣の違いによるズレを減らし、外国人観光客と地域住民の間の相互理解を深めるためには、外国人観光客に対して、訪れる前から、その観光地のルールやマナー、地域住民の生活、文化財の重要性を伝えていくことが重要です。そのための取り組みは多岐にわたります。空港や主要な新幹線駅、長距離バスターミナルでの到着時オリエンテーション動画の放映は基本です。動画では、具体的な禁止行為だけでなく、なぜそれが大切なのかを感情に訴えかける形で伝えることが効果的でしょう。多言語(英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語に加え、近年増加著しいタイ語、ベトナム語、インドネシア語など東南アジア言語にも対応した)でのイラストやピクトグラムを多用したわかりやすいサイン・パンフレットを、観光スポットの入口や交通機関内、公衆トイレなど、必要な場所に設置するのもアイデアのひとつです。そして宿泊施設(特に民泊やゲストハウス、小規模旅館)を通じた情報提供は極めて重要です。チェックイン時に、多言語のルールブックや地域マップを配布することも大事でしょう。さらに、SNSや動画プラットフォーム(YouTubeやTikTok)を活用し、ポジティブな形で現地のルールやマナーを発信する継続的な啓発も有効でしょう。ポイントは、禁止事項をただ羅列して観光客を威圧するのではなく、「なぜそのルールやマナーが大切なのか」(地域住民の日常生活を守るため、貴重な文化財を未来の子供たちに残すため、美しい自然環境を保全するため、みんなが気持ちよく過ごすため)という背景や意義を、共感を呼ぶストーリー性を持って理解してもらうことにあります。観光客が「地域の一員として協力したい」「敬意を持って行動したい」と思えるようなメッセージングが成功の鍵です。また、地域住民と観光客が直接交流し、互いの文化や考え方を知り、理解を深める機会を意図的に創出することも重要でしょう。地元の方との交流カフェ、職人技の体験ワークショップ、家庭訪問型の食事体験(民家でのホームディナー)、地域の祭りへの参加などが例として挙げられます。
地域住民参画の仕組みづくり
オーバーツーリズム対策を持続可能なものにし、地域社会全体の合意を形成するためには、何よりもその影響を直接的に受けている地域住民の理解と協力が不可欠です。そのためには、観光政策や具体的な対策の策定段階から、住民の意見を反映する仕組みを確立すべきです。住民説明会の定期的な開催、ワークショップへの住民の参加など、多様な方法で住民の声を拾い上げ、観光政策に反映させるプロセスを透明化すべきでしょう。
観光がもたらす課題(不便さ、環境負荷、安全不安)と利益(経済効果、地域活性化、文化交流)についての情報を、自治体や観光事業者から住民へ丁寧に共有する努力も怠らないようにしましょう。さらに、観光による収益が、住民の生活の質の向上や、観光公害対策に確実に還元される仕組みを作ることも、住民の納得感と協力を得る上で重要です。例えば、観光税や特定施設の入場料の一部、クルーズ船の寄港料、あるいは駐車場収入の一部などを、道路や歩道の補修・拡幅、ゴミ処理施設の増強・清掃員の増員、公共トイレの増設・清潔な管理の維持、生活環境を保全する基金(騒音対策設備の設置、景観保全のための修景、緊急車両確保のための道路管理、住宅街の防犯灯増設など)に充てることを示すことができるとよいでしょう。住民が「観光客増による不便の解消に、確かにこのお金が使われている」と実感できる透明性が生まれると信頼が生まれると思います。同時に、地元中小企業(旅館、飲食店、土産物店、体験コンテンツ提供者など)が、増加する観光需要を確実にビジネスチャンスに繋げられるような支援策を充実させ、利益が地域内で循環する仕組みを強化できるとよいでしょう。住民一人ひとりが、外国人観光客の負担部分だけでなく利益も実感できるような仕組みを構築できると、オーバーツーリズム対策になるのです。
効率化、分散化、新体験創出による観光の質的転換
テクノロジーの進化は、オーバーツーリズムの緩和と、観光の質的転換に大きな可能性を秘めています。まず、リアルタイムの混雑状況を可視化し、観光客に混雑回避や分散を促すスマートフォンアプリケーションは既にいくつか運用されていますが、さらにその精度を高め、予測機能を強化し、代替ルートや空いている周辺スポットの具体的な情報を提供するものへと進化させていく必要があると考えられます。GPSデータやSNSの位置情報投稿、監視カメラの映像解析(プライバシーに配慮しつつ)、さらには各施設の入場者数データなどをAIで統合・分析し、混雑パターンを予測する高度なシステムの構築も有効になってくるでしょう。
観光客は、目的地の混雑予測や周辺の混雑状況を事前に知り、旅程を柔軟に変更できるようになります。さらに、バーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)といった先端技術を活用すれば、混雑する実空間での体験を補完したり、物理的に立ち入れない場所(非公開の文化財内部、過去の景観、混雑を避けた時間帯の様子)や、混雑が予想される時間帯にバーチャルに体験できる「デジタル観光」「バーチャル観光」の可能性が大きく広がります。
例えば、混雑する寺院の本堂内部をVRで詳細に見学したり、過去の町並みをARで再現しながら街歩きを楽しんだりすることが可能になります。これは、混雑緩和に寄与するだけでなく、高齢者や身体に障害のある方、あるいは時間的制約のある方など、多様な人々の観光参加を促すことにもつながる、インクルーシブな側面も持ちます。また、非接触決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済)の普及は、現金取引の煩わしさや言語の壁を減らします。それによって、観光地の中小小売店の販売機会にもなるでしょう。多言語対応の音声翻訳機やAI翻訳アプリの進化は、言語の壁を大幅に低くし、住民と観光客の間のちょっとした会話やトラブル時のコミュニケーション円滑にしてくれるかもしれません。デジタル技術を新たな価値を生み出す重要な手段として位置づけていきましょう。
持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)へ
オーバーツーリズム問題の根本的な解決は、観光客数の最大化という量の追求から、観光体験の深さや豊かさ、そして持続可能性を重視した質の追求へと、観光のあり方そのものを転換することにあります。これが「持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)」の核心です。具体的には、以下の三つの柱を統合的に実践してみてはいかがでしょうか。
環境面では、観光が環境に与える負荷を最小限に抑えることを最優先としましょう。CO2排出削減のための公共交通機関や自転車の利用促進、ゴミの削減・徹底した分別・可能な限りの持ち帰り運動の展開、水資源の節約、自然保護区域での定められた行動規範の厳守、動植物の保護や生物多様性への配慮などです。観光地は、環境保全の模範となるべきです。
社会・文化面では、訪れる観光地の文化や伝統、生活様式を尊重し、生活の保全に観光が貢献する形を目指しましょう。地域住民の生活を乱さないマナーの厳守、地元の祭りや行事への敬意ある参加(見物ではなく理解を伴う参加)、伝統工芸品の購入や職人技の継承支援、地元産品の消費(地産地消)による地域経済循環の促進、住民と観光客の双方向の文化交流の機会創出などが重要です。観光は地域文化の消費者ではなく支援者であるべきです。
経済面では、観光による経済的利益が、地域社会全体に広く還元される仕組みを構築しましょう。地元中小企業での消費促進、地域内での雇用創出と人材育成、地域通貨や地域ポイント制度の導入による地域内経済循環の強化、観光収益の一部を地域の社会資本整備や環境保全活動に再投資する仕組みなどが考えられます。利益が地域に根付き、住民の生活向上につながることが持続の鍵です。
観光地側も、単なるハコもの開発(大型商業施設や箱物博物館)や通過型の観光に依存するのではなく、地域固有の資源(自然景観、歴史・文化遺産、伝統技術、人々の温かさ、食文化)を活かした、本物の体験を提供する方向へと、観光コンテンツやビジネスモデルを本質的にシフトしていく必要があります。数より質と持続可能性を評価する観光へと、関係者全体の価値観を変えていく挑戦が必要です。
まとめ
オーバーツーリズムは、単純に「外国人観光客が増えすぎた」という表面的な現象では決してありません。それは、SNSによる情報拡散の爆発的加速、LCCやビザ緩和に伴う旅行の大衆化と気軽化、歴史的・地理的要因による観光地の物理的キャパシティの限界、国と地方の観光政策の不整合や遅れ、文化・習慣・価値観・言語の違いに起因する相互理解の不足、観光経済効果の受益者と負担者の乖離による恩恵の偏在、そして環境や文化財・自然遺産への過大なダメージなど、数多くの要因が絡み合って生み出された構造的な社会課題です。その結果、地域住民の日常生活の平穏が脅かされ、文化遺産や自然環境が危機に瀕し、ひいては観光地の魅力そのものが損なわれるという深刻なジレンマに陥っています。住民の間には疲弊感や諦め、ときには外国人観光客への反発感情さえ生まれ、観光業に携わる中小事業者も、将来への不安を抱える現実があります。
しかし、この問題は決して克服不可能ではありません。オーバーツーリズムの克服と、持続可能な観光地の未来を創る鍵となるのは、「持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)」への意志と、実現するための具体的な行動、そして共創(Co-creation)の精神です。観光客を単なる「消費する存在」「経済効果の数字」として捉えるのではないのです。
観光事業者、特に地元に根ざす中小企業は、量よりも質を重視した本物の体験を提供する役割があります。地域の資源(自然、文化、人、食)を深く理解し、それを活かした独自性のある持続可能なビジネスモデルを構築しましょう。デジタル技術の積極的な活用も、効率化と新たな顧客体験の創出、ひいては競争力強化の鍵となります。
地域住民には、観光がもたらすメリットとデメリットを客観的に理解し、将来の地域の姿について建設的な対話に参加する姿勢が重要です。
国(政府)には、単なる観光客数や消費額の数値目標を追い求める政策からの根本的な転換が求められます。地域の社会的・環境的な持続可能性を最優先に据え、それを支えるための法整備(観光基本法の見直し、自治体の規制権限強化)、財政支援(キャパシティ管理・分散策のインフラ整備、中小事業者支援、環境対策費)、そして「質の高い観光」「持続可能な観光」を国内外に強力に発信し、その価値を広める役割が期待されます。
オーバーツーリズムは、日本が真の意味での成熟した観光立国へと成長する過程で避けては通れない試練です。確かに、混雑やマナー違反、生活への影響に直面する住民の方々の辟易とする気持ちは理解できます。しかし、外国人観光客を単なる問題の根源と断じるのではなく、日本の魅力に心から惹かれ、その文化や人々との交流を誠実に求めてやってくるゲストであり、共に未来の観光地を創っていく仲間として迎え入れ、互いの立場を尊重し合う関係性を築いていくことが、問題の本質的な解決への第一歩となるはずです。
困難ではありますが、地域住民、観光事業者、自治体、政府、そして旅行者が、それぞれの立場で責任を果たし、知恵を出し合い、住み続けたいと思える魅力的な地域、そして訪れて心から感動できる、世界に誇るべき持続可能な観光地を、未来の世代に確実に引き継いでいけるのではないでしょうか。