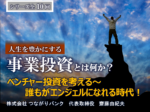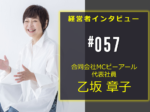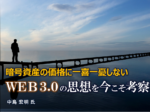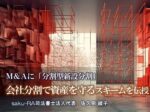ととのいラボ~手術治療の最前線!肺がん治療のエキスパートから学ぶ
- 2025/4/16
- 事業投資
区域切除術という手法
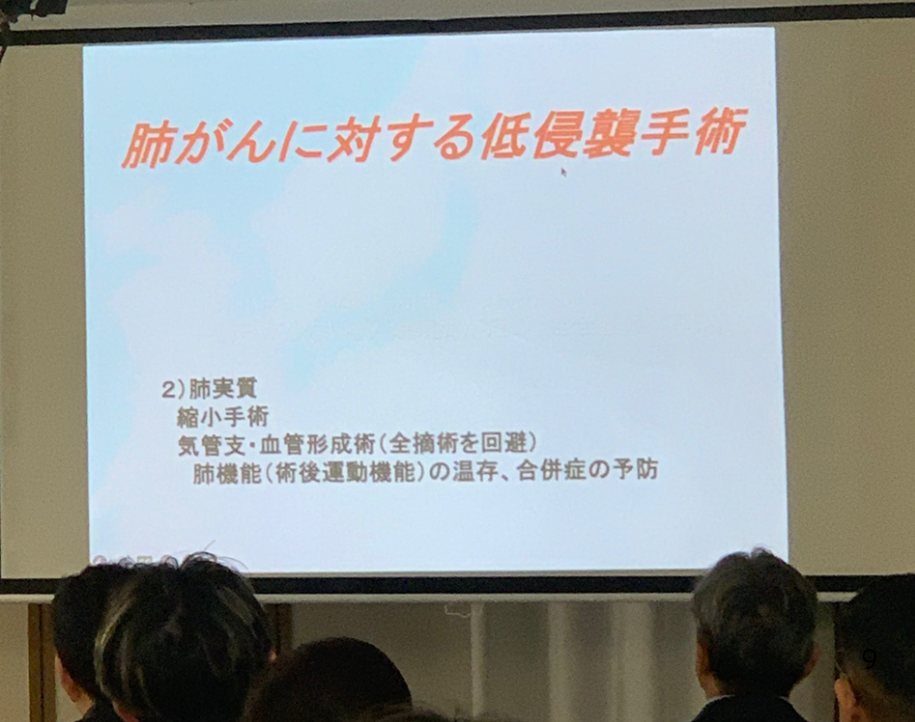
岡田教授提供資料より
肺がんにはⅠ期からⅣ期まであり、Ⅳ期は末期も含めがんが進行していて体中にがんが回っている状態ですから、手術はできませんので多くは薬物療法が中心になります。
肺がんの手術の対象となるのは、Ⅰ期からⅢa(前半)期まで。
がんの切除は、どんどん小さく切る方に移行しています。
その背景には、CTやPETなどの画像診断が進歩したことと、検診が普及したことにより小型の肺がんが多数発見されていることが挙げられます。
特に肺がんの手術においては肺活量を残すということがほんとうに大事なんですね。
肺は一切再生しません。
だからこそ、肺胞、肺胞管、呼吸細気管支などの肺実質を温存することに意味があり、区域切除術が注目されているわけです。
肺実質を残す意義の証明
2年半前の2022年4月、世界2大医学雑誌の1つ英国学術雑誌「The Lancet」(以下、ランセット)に、日本で行われた臨床試験の成績が発表されました※。
区域切除の術式による生存曲線が一般的な肺葉切除よりもはるかに上回ってしまったからです。
もともとの考え方、この試験をやろうとした我々のアイデアとしては、区域切除が標準手術である肺葉切除と同等であることを証明し、より小さく切ることによって肺活量が残り手術後の患者さんの日常生活動作への影響を軽減する区域切除に価値があるというシナリオを書いていたわけです。
しかし、実際やってみると、世界が驚き、我々も驚くほど想定していた以上の生存率が実証された。
すなわち、がんを治すよりも機能を温存する方が優先されるということが証明できたんです。
この事実が世界で最もインパクトがある雑誌に掲載されたことよって、世界中の教科書やガイドラインが変わるわけです。
肺がんの縮小手術である区域切除は、標準手術とされてきた肺葉切除よりも手技的には難しく、難度も高い。
私は、この区域切除のエキスパートとしてこの20年間、教科書を書いたり、海外に行って発表したり、ライブ手術を行ったりしてきました。
この度、このオールジャパンが行った全国的な臨床試験によって、小型肺がんの標準手術として肺葉切除に変わって区域切除が承認されました。
その結果、世界的な医学雑誌ランセットに掲載され、世界にも認知されることになったのです。
肺がんは大きく切除すべきという過去の概念から、肺の機能を温存し、がんは的確に小さく切除するという方向へ大きく変わったんです。
悪性度の高い肺がんでは無理だろうと言われていた区域切除が認められたという大きな転換です。

ととのいラボ~岡田教授セミナーに参加された方々と記念撮影
患者さんからの手紙
雑誌に掲載された「5年先の光が見える」というタイトルの患者さんからの手紙を紹介します。
拝啓
先生には、お忙しい日々をお過ごしのこととお察しいたします。
私は、2007年2月26日、兵庫県立がんセンターにおいて長時間にわたる手術をしていただいた者です。
最初、手術は難しいので、放射線治療をしましょうということでした。
でも、甥の紹介で、岡田先生のセカンドオピニオンを受けることができました。
先生からは、今手術を受けるのは危険なので、この段階では放射線治療をし、がんが小さくなったら手術ができるので頑張りなさいと言われ、結果として小さくなったので手術を受けることができました。
手術前の説明として担当医から、「すごい先生に診てもらえてよかったね」と言われた言葉を覚えています。
後に、担当医から、岡田先生は日本でトップクラスの先生だと聞いた時、私はなんと幸運なんだと思いました。
また、手術後先生が病室に来られて、「最高の手術をしておいたからね」と言ってくださいました。
先生が帰られた後、同室の人から「すごい言葉やね」と言われ、とても嬉しかったことを覚えています。
手術後の5年間の最も支えになった言葉です。
もう1つは、担当医から、ずっと向こうに5年先の小さな光が見えるよと言われたことです。
あの病院には素晴らしい先生がおられるから、安心して治療しなさいと言われました。
その先生は岡田先生だったんですね。
退院してから、先生がテレビで対談し、肺がんの神の手として紹介されていたのを観て、改めて先生のすばらしさに感動し、何回も繰り返し観ました。
おかげさまであれから5年が経過して転移もなく、放射線科の診察も終了しました。
あとは定期的に検査を受けるのですが、このまま転移もなく生きられることを願うばかりです。
先生は今まで何万人もの手術をされているので、私のことは覚えていないと思いますが、私にとっては命の恩人です。
もし手術をしなかったら、今頃はこの世にいなかったことでしょう。
これからどれだけ生きられるかはわかりませんが、今生きていることに幸運を実感しています。
だからどうしても先生にお手紙を書きたくて出させていただきました。
失礼をお許しください。
先生はこれからたくさんの肺がんで苦しんでいる人たちの手術をされることでしょう。
どうぞお体を大事にされて、1人でも多くの患者さんを助けてあげてください。
今後の先生のますますのご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。
本当にありがとうございました。
岡田先生談
2012年3月23日、広島大の患者さんから1通の手紙をいただいた。
2007年2月末、兵庫県立がんセンターでのこの患者さんの手術は、私がセンターで執刀した最後の手術で、患者さんは左上葉の肺がんでリンパ節転移がすぐ認められ、上下中核に及んでいた。
この年の4月1日に広島大学への移動が決まっていたため、直前の3月は自ら後進の指導をすることに専念していた、その直前のことである。
肺がんステージ3bに近い3a、がんの完全切除の可能性は極めて低い状況である。
この状況での5年生存率は20%以下、実際には一桁と推測された。
結果的には、「5年先の小さな光が見えるよ」が実現したわけである。
神様に感謝するしかない。
再発の可能性が高いと私が考えていたことは十分にご本人にも伝わっていたのだろう。
この患者さんは常に死と向き合って生きてきて、やっと5年経ったのだと思えば、本当にラッキーでしかないのかもしれない。
このような患者さんがいることを忘れてはいけない。
論理的なエビデンスと手術の巧みの両者を追い求めること、最高の結果をもたらすのはガイドラインではなく医師の強い志であることを、この証言から改めて教えられます。
※参考:国立がん研究センター
「3 cm以下の早期肺がんに対して肺機能温存手術である区域切除の有用性を証明-The Lancet Respiratory Medicineに論文発表-」