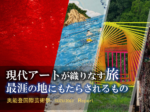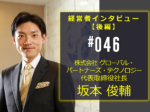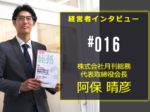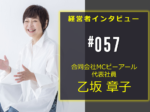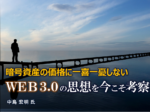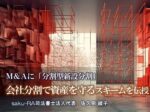里山の人々の想いと地域資源をアートで紡ぐ芸術祭20年の挑戦
- 2020/12/25
- インタビュー
目次
芸術祭による地域おこしの始まり
――越後妻有トリエンナーレの作品数は1,130作品もあるそうですね。アーティストの方々はどうやって集めるのですか?
関口氏――北川氏が中心になって国内外の著名アーティストを口説き理解を得たことで、多くのアーティストを集めることができました。
海外でも都市部の街単位でアートを作る試みはあっても、地域という広範囲でここまで深く地域の生活と関わってアート空間がつくられ、しかも長期間に渡って開催する事例は他にないと思います。
里山がもつテーマである、地域の衰退だったり、グローバリゼーションだったりに共感してくれたり、単純に面白みを感じてくれたり、特に若手は当時アート発表の場が今ほどなかったことから挑戦心を感じてくれたのでしょう。
アーティストにとっても、旅する感覚で新たな自分を発見し自己変革につながる場になると感じてくれていたと思っています。
“越後妻有トリエンナーレ”に共感する人々との連帯
――芸術祭により、地域の方々の意識はどのように変わっていきましたか?
関口氏――人里離れた場所で、時代に取り残された感覚を持っている人もいますが、変わっていく方は沢山います。
アーティストは土地に敬意を払う人が多く勉強熱心。
基本的には地域の人たちの協力なくしては成し遂げられないことばかりですから、地域の人も「手伝ってやるよ!」と優位になれるんです。
自分の得意なことが生かせる。
そして、外から来たお客さんが土地の人間より地域のことを知っていたりするので、焦って自分の土地やアートについて勉強する。
そんな様々な媒介があって少しずつ開かれていくのを感じます。
人によって捉え方はそれぞれですが、取組に乗ってみようとする人たちから面白さや楽しさが伝染して人の輪が広がっていきました。

茅葺き民家を「やきもの」で再生した、レストラン・宿泊施設としてもアート作品としても人気のある「うぶすなの家」。地域の人々が地域の食材を使った料理でもてなします。
出典:https://www.echigo-tsumari.jp/travelinformation/s_ubusunahouse/
芸術祭20年の歩み
――2000年の初開催から20年経ちますが、地域の人々との関わりに変化はありますか?
関口氏――長年の関わりの中で、関わりのなかった集落が参加してくれたり、家を貸してくれたり、現在進行形で広がりを感じます。
でも、20年経って、開始当時の中心メンバーが高齢化する中で変化も出てきた。
文化の伝承についていえば、土地に住んでいるから伝承されるというわけでもないんです。
例えば、十日町の美しい棚田が人手不足で放棄されたことに、地元の人はあまり想いを寄せなくても、逆に外部の人が心を痛め後世に伝えていこうとする場面もある。
そうすると、住民という定義はなんだろうと思ったりします。
今はオンラインで、東京にいながらも、地域にいるのと近い感覚で想いを共有できますから、関わり方も次のステージを考えないといけないなと思っています。
“奥能登国際芸術祭”での取り組み

奥能登国際芸術祭2017年の作品。のと鉄道旧上戸駅の駅舎のシルエットをなぞった骨組みだけの構造物を、駅舎の上部に角度を変えて重ねている。
奥能登国際芸術祭公式サイト(https://oku-noto.jp/ja/artist36.html)より
――関口さんは、今は奥能登国際芸術祭2021年開催を目指して活動されていますね。奥能登と越後妻有、文化的にもだいぶ異なりそうですが、地域とのかかわり方はやはり違いますか?
関口氏――はい。2021年の開催で2回目となります。越後妻有とは全然違いますね(笑)
奥能登は海が目の前ですから、地域の人々は海の向こう側への意識を持っていて、未知への好奇心が強い気がします。
アートや芸術祭の受け入れも早い気がしますが、まだ分からないですね。
地域によって人の想いは様々ですから。どこの事例が当てはまるというものではないと思っています。
地域に眠る可能性を引き出す芸術祭
――来年は全国4か所で芸術祭が開催されますね。地域に果たす役割ってなんだと思われますか?
関口氏――地域のポテンシャルや人々が自分で閉じ込めている内なるものをどこまで引き出すか、だと思いますね。
アーティストとの関わりの中で、自分の中に持っている制約や常識を取り外してもらうきっかけや発見になっているといいなと思います。
――最近、アートビジネスが話題ですね。アートをビジネスの場に活かそうとするアート思考に関する本がベストセラーになったり、個人的にアートを所有しようという人が増えたり、作品の分割購入権を持てるプラットフォームも話題です。アートがより身近になったことをどう思われますか?
関口氏――今までアートは、よく分からない狭い世界としてなかばシャットアウトされていましたが、沢山の人が関心をもってくれたことで、開かれていくいい傾向だと思います。
アートには多様な考え方があるので、100円アートでも芸術祭でも美術館でもふれることで、未知のものに寛容になれる姿勢は大切です。
ただ、アートをビジネスに直結させても、問題解決の手段として即効性はないので、すぐにはうまくいかないでしょう。
問題解決の方向性や閉塞感を破る勇気を与えてくれる作家や作品との出会いがあるかも、というところでしょうか。共犯者みたいな。
結局、それぞれ自分の中にあるもので課題を解決していくのだと思います。
アートも曖昧で、学問の世界のようには分類されにくいですし、何がアートなのか言えないということもアートなんだろうと思います。
アートの多様性は、自分の中の言葉にならないもののアウトプットが源泉なのかもしれないし、お祭りだって落書きだって日常にあるものをアートとして捉えれば、そんな敷居の高いものではなく誰でも親しめるものですね。
「アート思考」というといきなり身構えちゃいますけど、伸びやかさを大切にして、まずは、沢山のアートに触れて五感で感じてみてはいかがでしょう。
アートという多様なものさしで人生を豊かに

アートフロントギャラリー ここでは絵画を購入することも可能 (Z-EN編集部撮影)
――アートを購入したい経営者の方に、どのような目線でアートを手元に置いたらよいのかアドバイスをお願いします。
関口氏――私は、コレクターが増えるのは賛成です。
コレクションすることは支援するということで、未知のものを応援しないと時代の流れが止まってしまいます。
自分と通じ合えるものはこの世界にそんなに多くないと思っています。
アートを見ていてある部分、すごく分かる!気になる!という感覚を信じて手元に置いてはどうでしょうか。
アートでもなんでも、そういった”自分のものさしになりうるもの”があることは人生を豊かにすると感じています。
関口さんがオーガナイザーとして関わる「奥能登国際芸術祭」の記事はこちら
「奥能登国際芸術祭」の仕掛けは、開かれた現代アート×過疎地