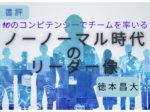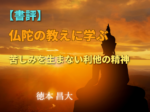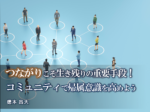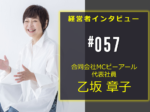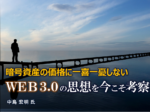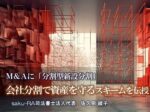【書評】購買プラットフォームが実現する“失敗しないDX”
- 2025/4/3
- 書評
目次
DX最適化の道標“KOBUY Journey”
「問題」の発見は、「現状」の詳細な分析と、目指すべき「あるべき姿」の比較から生まれます。現状とあるべき姿の差こそが「問題」と認識すべきものです。(阿保晴彦)
著者の一人、阿保氏は、企業が間接材購買における問題を発見するための重要な視点を示します。
企業は、部署ごとに「あるべき姿」が異なり、各部門が自部門の目標に向かって個別に動くため、全体の最適化からかけ離れてしまう事態が生じます。
これが全社的な効率化やコスト削減を困難にする問題の複雑さにほかなりません。
これらの問題を解決するために、KOBUYの導入と新しい業務フローへの転換が重要になります。
しかし、部門横断的な「あるべき姿」の構築は容易ではなく、ある部門の最適化が別の部門の非効率を生むことさえあります。
そこでKOBUYは、間接材購買全体の「あるべき理想形」を「KOBUY Journey」として提案しました。
KOBUY Journeyは完璧なものではなく、おおよそ70点のビジョンを示すにすぎませんが、「自分たちの組織や意識の中で何を変えるべきか」というイメージを持つための道標となります。
つまり、KOBUY Journeyとは、DX化と全体最適化の道筋を示し、企業独自のDXの達成に向けたカスタマイズとともに使い勝手の調整を続けながら業務改善を実現するツールです。
KOBUY Journeyは、以下の5ステップで進められます。
- 業務改革プロジェクトの組成
- 現場業務の見える化
- 間接材購買プラットフォームKOBUYのカスタマイズ
- 間接材購買のKOBUYへの集約
- 運用確認と改善伴走
これらのステップを通じて、企業は自社の購買管理の成熟度を実態で判断し、段階的な改善を実現できます。

働き方改革の環境整備にも役立つ
多くの企業がデジタル化を推進する中で、しばしば後回しにされがちなバックオフィス機能としての購買・調達部門の変革に本書は焦点を当て、企業全体の競争力向上につながる視点を提供しています。
購買・調達部門の変革は、単なるコスト削減にとどまらず、企業の持続的成長を支える戦略的機能として再定義されるべきものなのです。
さらに注目すべきは、本書がデジタル技術の導入自体を目的とするのではなく、あくまでも業務プロセスの改善や人材の能力向上、そして取引先との関係強化といった本質的な課題解決のための手段としてデジタル技術を位置づけている点です。
KOBUYの考え方では、テクノロジーはあくまでも人間の創造性や判断力を拡張するためのツールであり、人間の役割を代替するものではないという視点が貫かれています。
KOBUYが提唱する「ブルシットジョブ(無意味な仕事)」からの脱却という概念も興味深いものです。
単純作業や付加価値を生まない業務からの解放により、人間が本来持つ創造性や専門性を発揮できる環境を整えることの重要性が説かれています。
特に、日本企業に根強く残る非効率な業務プロセスや形骸化した慣行の見直しを促している点は、現代の働き方改革の文脈においても価値ある提言と言えます。
バイヤーとサプライヤーをマッチング
KOBUYが、多様性がより高まる時代において、課題解決の武器としようとしているのが、「KOBUY経済圏」と呼ぶビジネスの場の醸成です。KOBUYはすでに、バイヤー企業とサプライヤーネットワークのマッチングの場となっており、サプライヤー企業にとっては「ビジネスの場」として認識され、プラットフォームへ参画することのメリットが理解されています。
KOBUYのプラットフォームは、単なるデータ管理を超え、AIとデジタル技術を活用したエコシステムとして進化を続けます。
バイヤーとサプライヤーがつながることで新たな価値が生まれ、その連鎖が広がることで、企業全体の購買活動がより最適化されます。

KOBUYは、購買のデジタル化を超えて企業間のつながりを強化し、KOBUY経済圏を形成していくことを目指すものだからです。
そこでは、AIを活用したデータ分析により業務のムダを削減し、最適な購買体験が提供されるため、結果、企業はコスト削減や業務効率化だけでなく、より高度な購買戦略を実現することができます。
さらに今後、中小企業にも開放されることで、新たなビジネスチャンスと最適な購買体験が提供されるうえ、新たなイノベーションを生み出す場にも生成されていくことでしょう。
データ活用やAIの進化によって企業同士の協力が促進され、新たなサービスやビジネスモデルが誕生する可能性が広がっています。
このように、今後はAIを活用したエコシステムの発展により、KOBUY経済圏はさらなる成長を遂げ、すべての参加企業に新たな価値をもたらしそうです。
阿保晴彦氏の過去記事はこちら
出典:失敗しないDX(阿保晴彦, 橋爪康太郎)の書評
この記事は著者に一部加筆修正の了承を得た上で掲載しております。

著者:徳本昌大、松村太郎(2024年8月6日発売)
世界で初めて時価総額3兆ドル企業となり、次々と革新的な製品を世に送り出すアップル。世界中の人々の生活にイノベーションを起こし、絶えず高成長・高収益を継続している魅力的な投資先でもあります。アップルは、ビジネスをどのようにして考え、実行し、成果を上げているのか。アップルのように考え、行動するには、どうすればよいのか。17のビジネスフレームワークを用いて、アップルを読み解きその成功の要因を明かします!